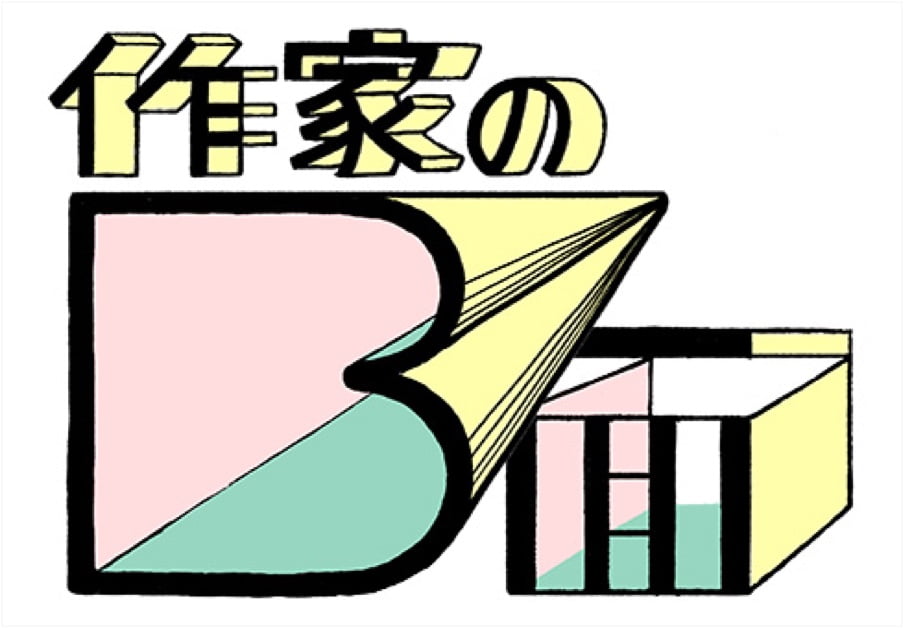- ARTICLES
- 【後編】植物はガラスの中であいまいになり、やがて未来に残る / 連載「作家のB面」 Vol.36 佐々木類
SERIES
2025.09.24
【後編】植物はガラスの中であいまいになり、やがて未来に残る / 連載「作家のB面」 Vol.36 佐々木類
Text / Yutaka Tsukadai
Edit / Eisuke Onda
Illustration / sigo_kun
アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。
今回登場するのは、ガラスに植物を閉じ込めた《植物の記憶》シリーズなどを手がけるアーティスト・佐々木類さん。前編では、幼い頃から通い慣れた間宮林蔵記念館を訪れ、同館や博物館、そして考古学から受けた影響について語ってもらった。後編では、彼女の制作の歩みとこれからの展望に迫る。
焼くことで分かる真実

ーーここからは作家活動についても伺いたいと思います。武蔵野美術大学ではどのようなことを学ばれたのでしょうか。
入った学科は工芸工業デザイン学科だったので、1、2年生の時はインテリア、車など様々なデザインや素材について学びました。その後、もともと興味のあったガラスを専攻します。そして卒業制作で大きな作品を作ってみたのですが、デザインよりもそういう、いわゆる作品制作のほうを追求したいなと思ったんです。
ただ当時は何のコンセプトもなく作っていて、日本も含めて進学先を探し、先生が一番面白そうな作品を作っているところを選びました。

《記憶の眠り》(2024) 北アルプス国際芸術祭2024出品作品 撮影:平林岳志
ーーそこから植物をなどを挟んで焼成する作風に至るまで、どんな変遷があったのですか?
ガラスにモノを入れて焼くのは「インクルージョン」と呼ばれる技法で、元々は科学者の人たちがガラスの中に異物を入れて、強度計算をするためのものでした。これを作品に転用したのはアメリカに留学していたころ、「懐かしさの欠如」を感じてたからなんです。見るもの全てが外国のものなので懐かしさがなくて、自分が幽体離脱したような感覚に陥ってたんです。そういう状態だと母親から送られてきたレトルト食品の袋とか、普通だったら捨ててしまうものに愛情を覚えるようになったんです。
それとアメリカにはセカンドハンドショップという日本でいうリサイクルショップがあって、家族や恋人への手紙とかが1ドルぐらいで売られていて。懐かしさや愛情がこもっているものが売られてるって皮肉だなと思いけっこう買ってたんですね。アメリカにいたころはこれらを挟んで、リスペクトしつつ保存、記録する作品を作っていました。
その後アメリカから日本に戻ってきたんですが、今度はリバースカルチャーショックみたいな感じで、日本に全く懐かしさを感じず、危機感を抱いて植物採集をやり始めたんです。2013年に瀬戸内国際芸術祭に参加した時も、知らない場所だから植物採集から始めました。その時に島の人からいろんな話を聞きながら、ガラスの間に植物を挟んだ作品に本格的に取り組みました。
たまに作品を見た人から「琥珀みたいですね」と言われることがあります。父方の祖父が琥珀の産地である岩手の久慈出身なので、家に琥珀があったり確かに身近ではあったのですが、直接的に参照してるわけではありません。博物館に通った体験やプライベートなど、いろんなものがつながった結果だと思います。

佐々木さんの私物の琥珀(上)とアンモナイトの化石(左)。石鹸トレーに入った青いガラスは「あいち2025」で発表した作品。廃ガラスの中にイチョウ葉の灰がうっすらと見える
ーー佐々木さんの作品は物質の記録、保存をテーマとしつつも、その物質自体は灰になってしまっているという逆説的な面白さがあると思います。
それは面白い観点ですね。ただ私にとって「焼く」という行為は、焼失とか破壊というイメージではありません。灰はこの世にある一番最後の状態です。もっともピュアな部分というか、真実みたいなものを、ガラスという長期間変化しない物質に保存するイメージです。
人も火葬すると骨だけになって「この人こんなに細かったんだ」とかが分かるじゃないですか。これは私が日本人だからかもしれませんが、焼くと浄化されるというか、そういう感じです。保存、記録をする前に、真実の状態に還元しておくことが大切なんです。今は標本でも色をキープできる作り方がありますが、そういうことには関心がなくて、植物に含まれている空気とか、目に見えない現象のほうに興味があるのかもしれません。
考古学的な可能性を秘めたアート

ーー前編で博物館のディスプレイに関心があったというお話を聞きましたが、ご自身の展示においても分類に基づいた配置を行っているのですか?
それが逆で、私は博物館的に分類されてない、いわゆる「驚異の部屋」(*1)にも関心があったりするので、作品を配置するときはビジュアルを見て並べることが多いです。空間の条件に左右されたりもしますし、カテゴライズはバラバラです。ただ隅を型取った《The Corner/ある家》のような作品は型を取った順番を意識しています。なので並べ方は作品によって違うかなというところです。
*1……近世の西欧諸国において、王侯貴族や学者たちが不思議や驚異に感じた珍品器物を分野を隔てることなく展示したコレクションのこと。
見た人が違いや共通点を見つけたり、そういった気付きを与えたいと思っています。だから配置をランダムにするのは重要かなと思っています。些細な違いを見つけてもらいたいんですね。カテゴライズしてしまうと、私の意志が入ってしまう。

《Corners at My Parents’ House》(2010-2024) 撮影:来田猛
ーー植物を採集する際にも記録を取られているそうですが、作品発表の際、そうした情報は全てが観客に知らされているわけではありませんよね。それはどうしてなのでしょうか?
私にとっては曖昧な状態がいいんです。具体的な場所とかは示さないで、むしろモノとか温度、匂いといったことを示します。曖昧にすることで、鑑賞者が見たときに場所を想像してもらったり、自分の記憶と結び付けたりすることで、私のプライベートと共有できる部分が生まれるんじゃないかなと思っています。時々「色は付けないんですか?」とか言われるんですけど、そういった特徴づけはあまりやりたくありません。


ーーでは採集時の記録は、ご自身のためなんでしょうか。
ある意味日記をつけてる感じで、自分のため、作品のためというよりも、自然とやっている感覚です。ただ植物の名前を聞かれることがあるので、そういう意味では作品のためでもあります。ただそれを文字として示すとそれに見る人が引っ張られちゃうので、そうしないようにしてます。ただ可能性としては、テキストだけの、なにかエッセイじゃないけど、そういうのをやってみたいという気持ちはあります。


《植物の記憶 / Subtle Intimacy 2012-2023》(2023) 収蔵:金沢21世紀美術館 撮影: Nik van der Giesen
ーー佐々木さんの作品は植物の形態がそのまま残っているため、将来考古学的に見る人もいるかもしれませんね。
そうですね。特に温暖化が進むと、今ある植物が数十年後には見られなくなってるかもしれません。この日常で見てるものが非日常になる。そういう意味では琥珀っぽいかなとも思います。ガラスは半永久的にこのままなので、2万年先も残っている。以前自然科学系の学者の方から「新しい種の保存」と言っていただいたこともあります。「灰を解析したら遺伝子の情報が残ってるんじゃないか」という人もいて、もしそこから植物が復活したらジュラシック・パークの世界ですよね。
でもそういう話になるのも、ガラスがサイエンスにもアートにも近い素材だからなのかなって思います。ガラスは経年には強いけど衝撃には弱く、儚い。光に対しては反射もするし、内包もする。透明なものもあれば、不透明なものもある。構造的には固体でも、液体でもない。相反する特性や、曖昧さのある面白いマテリアルなんです。
植物があるから話せること


ーー芸術祭などで発表されるその土地に関連するサイトスペシフィックな作品は、どのように制作していますか?
リサーチも兼ねて現場に行って、色々お話などを聞かせてもらいます。普通に聞いても話してもらえないことも、植物を通すといろんな話が出てきます。割と民俗学に近い気がしています。あとは今の地図だけじゃなくて、ちょっと昔の地図も見るようにして、昔は何に使われていた土地なのかを調べたりします。かつて畑だったところに生えていた植物の遺伝子は今現在どうなっているのかとかを実際に見て確認したり、考えたりしながら自分の中にその地域のイメージを膨らませます。

ーーあいち2025への参加も発表されていますが、どんな作品を制作予定ですか?
私は瀬戸市にある数年前まで営業していた銭湯全体を使ったインスタレーションを展示します。瀬戸といえば焼き物のイメージがあると思うんですけど、そういった窯業がどのようにその地域全体に関わっていたのかをひも解いていきたいと思っています。
例えば瀬戸では粘土を採掘するために普通は農地や住宅地になる山が、採掘のためにそのままになってるんですね。なのでそこでは農地のように様々な植物が植えられずに、自生してる植物が残っています。あるいは住宅地にならないから湿地が残ってたりとか。あと採掘のために切り崩されてしまう山と違って、神社は守られているので太古の植物が残っていたりします。そういう事例をカテゴライズして、現地の廃ガラスも使いながら、ストーリー仕立てにして見せたいと思っています。
こういうふうなアプローチをしようと思ったのも、瀬戸には愛知県陶磁美術館など産業としての瀬戸物についての施設やそこでの研究があるにも関わらず、多様な粘土が採掘できるようになった自然史的な、つまり気候や地球環境を踏まえたリサーチがあまり蓄積されていないかもしれないと思ったからなんです。なのでわたしは植物を通じて、そうした側面を表現したい。異なる視点から見ると、また焼き物も違って見えるかなと思っています。

Museum Date
間宮林蔵記念館
18世紀後半にこの地で生まれ、江戸を経て北方で活躍した探検家・測量家「間宮林蔵」を顕彰するため、旧伊奈町が整備した博物館です。館内では、林蔵ゆかりの資料や彼が生きた時代背景をテーマごとに紹介。全国から収集した貴重な資料や子孫宅に伝わる遺品、関連史跡の情報などを交え、林蔵の足跡をわかりやすく展示している。隣接地には林蔵の生家も残されており、併せて見学することも可能。
◾️住所
茨城県つくばみらい市上平柳64-6
◾️開館時間
9時~16時30分
◾️休館日
毎週月曜日・12月28日~1月4日(月曜日が祝日・休日と重なる場合は次の平日)
Information
国際芸術祭「あいち2025」
■会期
2025年9月13日(土)~11月30日(日)
■会場
愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかほか
「あいち2025」公式HPはこちら
「ただ一輪の薔薇、それはすべての薔薇」ー国際芸術祭「あいち」2025に寄せて
from Aichi Triennale
佐々木類(SASAKI Rui)、冨安由真(TOMIYASU Yuma)
■会期
2025年10月29日(水)~11月24日(月)
10:00~19:00 ※最終日は16:00閉場
■会場
松坂屋名古屋店
本館8階 ART HUB NAGOYA open gallery
(愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1)
松坂屋名古屋店のHPはこちら
ARTIST

佐々木類
アーティスト
1984年高知県生まれ。石川県拠点。身近にある自然や生活環境にインスピレーションを得ながら、主に保存や記録が可能な素材であるガラスを用い、自分が存在する場所で知覚した「微かな懐かしさ」の有り様を探求している。北欧やアメリカを中心に滞在制作に招聘され、国内外の美術館で展示活動を行う。主な賞歴は、第33回Rakow Commission 2018(2019年、コーニングガラス美術館、米国)、富山ガラス大賞展2021大賞(富山市ガラス美術館)。ラトビア国立美術館、金沢21世紀美術館(石川)など作品収蔵多数。ニューヨークタイムズ紙などで作家特集掲載。
新着記事 New articles
-
INTERVIEW

2025.09.17
台湾出身アーティスト、デモス・チャンが語る。 「現代美術は、古いものに対して新しいチャレンジをすることで生まれ出てくる芸術」
-
SERIES

2025.09.17
名古屋の青木野枝の彫刻に吹き抜けた風を感じる / 連載「街中アート探訪記」Vol.44
-
INTERVIEW

2025.09.10
「怖い」ではくくれない、不思議な体験を──アーティスト・冨安由真が開く日常の異界
-
SERIES

2025.09.10
漫画家・井上三太に聞く「フォロワー数や受賞の有無だけで語れない、『教科書の太字にならない発明』の価値」 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.39
-
INTERVIEW

2025.09.03
「美術館は生まれ直しに行く場所」脳科学者・中野信子×3時のヒロイン・福田麻貴のアート体験から紐解く、強度のあるアートとその魅力
-
SERIES

2025.09.03
国立新美術館で開催する2つの展示から、各地のアートイベント・芸術祭まで / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2025年9月編