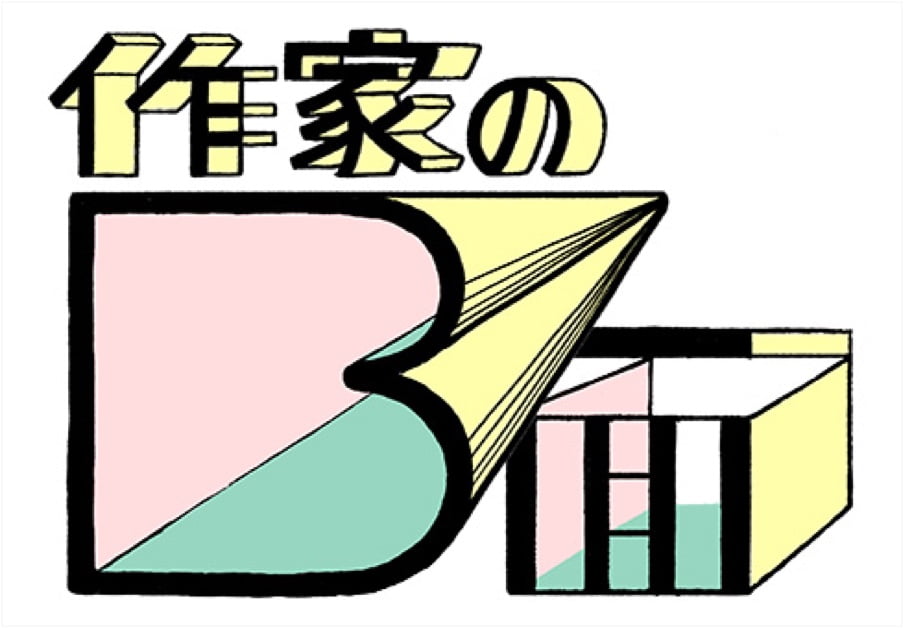- ARTICLES
- 【後編】 絵とは希望ですね。それはもう、大きな光 / 連載「作家のB面」 Vol.31 近藤亜樹
SERIES
2025.03.26
【後編】 絵とは希望ですね。それはもう、大きな光 / 連載「作家のB面」 Vol.31 近藤亜樹
Photo / Sakie Miura
Edit / Eisuke Onda
Illustration / sigo_kun
アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。
訪れたのは水戸芸術館。開催中の展示「我が身をさいて、みた世界は」を手がけた近藤亜樹さんに創作のインスピレーションとなったサボテンについてお話を聞いてきた。後編ではさらに近藤さんにとっての「描く」ということの本質に迫る。
描き続けた先にあるのは、ゼロだったんです

──本展のタイトルについて教えて下さい。
「我が身をさいて、みた世界は」という言葉は、サボテンを見ていて自然に出てきました。私も我が身をさいて新しい世界を見出すために、今までの自分を超えていこうと思いました。限界の限界の限界まで行きたい。でも、まるで山登りみたいなんですよ。何かがあると思って登るんだけど、結局山を登り続けても、その先にある頂上には何もない。だけどすごくボロボロになって登ったあとには、少し強くなった自分がいるんですよ。それが私にとって絵を描くことだと最近わかってきました。我が身をさいてみた世界は、私にとってはゼロだったんです。またスタートラインに立ったというだけだった。そこにはできあがった作品が広がっていき、ギャラリーに送られて、また何もなくなり、また白いキャンバスに向かう。そしてまた登るために、我が身をさき始めるんです、自分で。我が身をどこまでさけるかという挑戦は、強くなるための挑戦でもある。それによって、たくましく生きていける力が芽生えるんです。

左《我が身をさいて、みた世界は》(2024)、右《0》(2025) Copyright the artist. Courtesy of ShugoArts, Photo by Shigeo Muto
──一方で、さまざまな要因で、我が身をさけない人も多いと思います。特に社会情勢が不安定だと、何かを変えようとするよりも、変化を避けて今のままでありたいと望む「現状維持バイアス」が働くことも。
そうかもしれません。でも、動けない時間もその人にとっては大切な時間なんだと思います。それがマイナスな感情でもプラスな感情でも、どんな感情でも、その人にとっては大事な感情で持っていなきゃいけないものだと思います。今すぐじゃなくていいんです。やはり最初はつらいし、怖い。私もそうでした。だけど、それが明日か、10年後なのか20年後なのかわからないけども、その先で、我が身をさけるときは来るかもしれない。

──サボテン自身もそうやって日々成長しているのかもしれませんね。今日の胸元のサボテンブローチも素敵です。
水戸芸術館の案内スタッフ(ATMフェイス)と現代美術家・青山悟さんの共同プロジェクトとして制作されたブローチです。フェイスさんたちが日々の思いを形にして販売しているもので、今回の展示に合わせてサボテンをつくってくださいました。ミュージアムショップに登場する度に、人気で売り切れてしまうこともあるようですが、素晴らしい手仕事ですよね。こうやって表現が連鎖して、手に取った人がまたそれを大事にする。すごく理想的な循環ですよね。
音はかたちでも色でもなく、響きである

──これまでの花や植物をよくモチーフにされていますが、昔から身近な存在だったのでしょうか。
花の多い家で育ったんです。ただ、庭があったわけではなく、生花の方。人からもらったり、仏壇に飾ってあったり。母が好きだったんでしょうね。その影響か、私にとって花は、人の思いが必ず乗っかっているものでした。花は亡くなった人にも、生きている人にも寄り添っている。だから花を描いていても、それは花そのものを描いているわけではなく、私は誰かの気持ちや思いを描いているんです。花は太陽に向かって咲くじゃないですか。私が描く花の作品は全部、正面を向いています。それは、絵と出合う、あなた(鑑賞者)自身が光だから。あなたが生きていることは、それだけで価値がある。あなたは温かいということを表すためのものでもある。だから、私は思いを描いているんです。花と絵って言葉をもっていないのですが、だからこそ直接心に届くこともある気がしています。

近藤亜樹《ラブコール》(2024) Copyright the artist. Courtesy of ShugoArts, Photo by Shigeo Muto
──近藤さんは、作品の完成も絵から教えられると以前のインタビューで語っていました。絵と対話されているということでしょうか。
怖いですよ、意思を持ったときの絵は。あと一筆入れようとしても、もう触るなというオーラを出してきますから。だから触れられなくなって終わります。ただ今回制作した《ザ・オーケストラ》はなかなか終わりの合図を出してくれませんでした。

近藤亜樹《ザ・オーケストラ》(2024) Copyright the artist. Courtesy of ShugoArts, Photo by Shigeo Muto
──《ザ・オーケストラ》制作時のことを教えて下さい。
山形から仙台にバスで通うことがあり、高速バスから見える1本の黒く焦げた木から着想しました。森の方を見ると夕陽にたなびく雲があり、バスが動くと、電線が五線譜のように現れ、おそらく落雷によって黒焦げになった木が見えました。それがまるで指揮者のように思えたんです。そのときに私がバスの中で聞いていたのが、小澤征爾さんのオーケストラでした。その2週間後に水戸芸術館から個展依頼の連絡がありました。当時の館長は小澤征爾さん。これは運命的だと感じました。しかし、私は制作時に壁にぶち当たりました。音をどう表現すればいいのか、わからなかったんです。小澤さんにお話を伺えないかと思っていた矢先に、小澤さんは天国に旅立ってしまいました。
そしてもうわからないと思いながら、耳をふさいだ瞬間に、音はかたちでも色でもなく、響きであることに気づいたんです。その瞬間、あのときバスの中から見た情景と、小澤さんの存在が重なって感じられました。雷が当たり、焦げながらもなお立ち続ける一本の木も、小澤さんも、みんなの心に生き続けるんだな。そう思って描いた指揮者の姿は、赤く燃え上がる響きとうねりの不死鳥として表現しています。しかし、描けども描けども、絵が喋りかけてこない。音を描いている作品なのに、終わりの音が絵から聞こえてこないんです。
──どういう描き終わりを迎えたのか気になります。
《ザ・オーケストラ》の終わり方はすごかったですよ。脳の中に「ドン!」という大きな音が響いたんです。圧がすごくて、もうこれ以上手を加えるなと言わんばかりで、もう絵のそばに寄れなかったです。
絵に教えられてばかりいます


──《ザ・オーケストラ》もそうですが、近藤さんの作品からは生命力を感じます。
私が生命のあるものに感動しているからでしょうね。感動して、心が動いて、初めて筆が動くので。
──生命力とは対義的な位置にある「死」についてはどう考えますか?
私は夫を亡くしているので、死というものは常に意識せざるをえないものでした。あまりに突然だったので、心の準備もないままに夫はこの世を去ってしまった。そうなると余計に回復に時間がかかるんですよね。私は今も回復はしていないかもしれない。でも、私は死の世界は見ていないから、わざわざそれを描くことはできないんです。そもそも描こうとしたとしても、絵には悲しいまま現れてこない。
──絵と対峙するときに、悲しみが希望に変換されるのでしょうか。
わからないです。絵を描きながら、なんでこれが出てきたんだろうっていつも思います。制作している最中はなんでこれを描いているのかという意識はなく、8割ほど描き進めたあとに、あぁ、◯◯に反応して描いていたんだと気づくんです。それは描いている具体的な対象のことではなく、その奥にあるものに対する反応です。だから、ポートレートシリーズを描いていても、人に反応しているわけではなく、人の心に反応しているんです。私に関していえば、絵よりも正確なものはないんですよね。私自身よりも正確で、正しいと思う。絵に教えられてばかりいます。

──絵が思考の言語化につながっているんですね。
そうですね。私はそもそも映像や舞台芸術などにも興味がありました。でも、結果的に絵を選んだのは、重力がなかったから。自分が思った世界を描くと、作品はそのままの状態で留まってくれるじゃないですか。想像はすぐに消えてしまうけれど、絵は描くと残る。だから、絵である必要があったんです。私は、忘れ去られてしまう思考を残しておきたかった。作品に向かい、毎日毎日描けば描くほど、絵の具は乗っかります。すると、絵から実体が出てくるんです。自分の想像から出てきたもののはずなのに、私とは違う実体として現れるんです。

近藤亜樹《クマ次郎とテフロカクタス》(2024) 部分
──絵を描きながら、自分について考えることはありますか?
絵と対峙していると、私は自分の小ささをいつも感じます。自分が想像することは、世界のほんのひとかけらでしかないということに気づくんです。そして想像の世界はとても大きい。生きている心には、想像の世界が無数にあるんです。それが芸術の素晴らしさだと私は思います。
──近藤さんにとって、絵とはなんですか?
希望ですね。それはもう、大きな光です。

Information
近藤亜樹:我が身をさいて、みた世界は
躍動感溢れる筆遣いと力強い色彩の絵画で知られる近藤亜樹の個展。本展では、生命の祝福、他者と共に在ること、2022年以降ますます切実さを帯びる災害や戦禍にある人々への想い、葛藤とレジリエンスなど、近藤亜樹の作品をとおして「生きること」と「描くこと」が切り開く世界に迫ります。
会期:2025年2月15日(土)~5月6日(火・振休)
会場:水戸芸術館 現代美術ギャラリー
住所:茨城県水戸市五軒町1丁目6−8
公式サイトはこちら
ARTIST

近藤亜樹
1987年北海道生まれ。2012年サンフランシスコ・アジア美術館での企画展「PHANTOMS OF ASIA: Contemporary Awakens the Past」に10メートルを超える大作絵画《山の神様》を出展。以後、描くことで現実に向き合う自らの創作を探求し、2015年には約14,000枚の油彩と実写を組み合わせた鎮魂の映画《HIKARI》を発表するなど、絵画表現の可能性を拡げてきた。2020年から山形県を拠点に活動している。 主な展覧会に「わたしはあなたに会いたかった」(個展、シュウゴアーツ、2023年)、国際芸術祭「あいち2022」(2022年)、「星、光る」(個展、山形美術館、2021年)、「高松市美術館コレクション+ 身体とムービング」(高松市美術館、2020年)、「絵画の現在」(府中市美術館、2018年)など。受賞歴に2022年VOCA奨励賞、2023年絹谷幸二芸術賞などがある。
新着記事 New articles
-
SERIES

2026.02.25
ダニエル・ビュレンの世界で最も無難なストライプをお台場で観る / 連載「街中アート探訪記」Vol.49
-
NEWS

2026.02.25
「ART ART TOKYO」が大丸東京店で開催 / 半年に一度のアートイベント!
-
NEWS
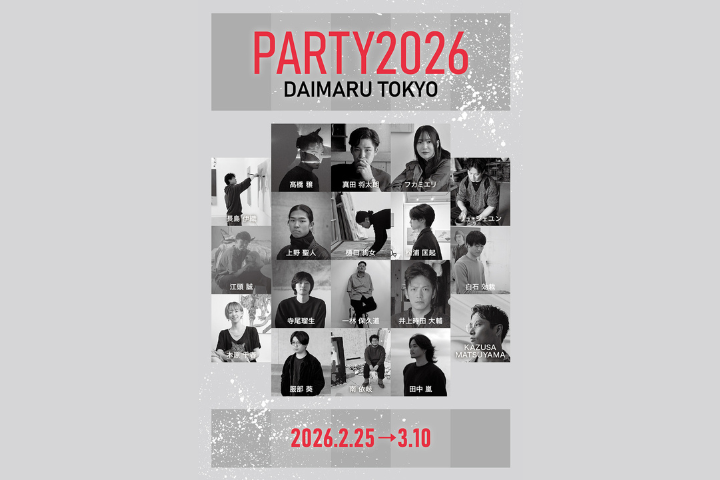
2026.02.25
大丸東京店で 企画展「PARTY2026」が開催! / 気鋭の若手アーティスト18名による展覧会
-
SERIES

2026.02.18
アーティスト松山梨子 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.43
-
SERIES

2026.02.11
光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3
-
SERIES

2026.02.11
「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44